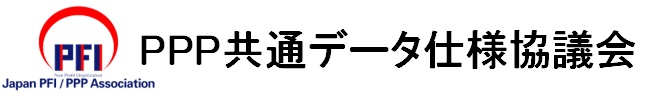[付録] デジタルは難しい?
近所の皆さんとお話ししていると良く「私はもう年寄りだからデジタルはわからない」という方がいらっしゃいます。恐らくそれは筆者も含めたエンジニアや行政やメディアの怠慢が生んだ誤解の様な気がしています。何故かというと、デジタルが分からないという方に「テレビはご覧になりますか」と聞くと必ず「うん、良く見るとよ」などという答えが返ってきます。テレビだけでなく自動車も電話も全てデジタルの塊りです。でもご近所の方はそれを「デジタル」には分類しておらず、難しいとは感じていません。何故か。。。
デジタルにはデジタル技術を活用した通信・金融・制御・認識などの各種機能がありますが、もうひとつデジタル特有インタフェースというものがあります。インタフェースとは、PCや案内表示板などの操作端末やスマホなどの携帯端末があります。自動車やテレビの場合はアナログ時代の操作性をそのまま維持したままでデジタル化し、デジタル特有のインタフェース(テレビならdボタンなど)は知らなくても操作できるように工夫されています。つまり、インタフェースはアナログ風なのです。これに対して、スマホに代表されるデジタル機器はアナログ時代とは全く異なるインタフェースにになってしまいました。これがデジタルアレルギーを作っているのではないでしょうか。つまり、デジタルアレルギーではなく新インタフェースアレルギーなのだと思います。
例えば防災関係者と話をしていると、災害に備えて年寄り向けのスマホ教室が必要だという話が出てきたりします。平時にデジタルインタフェースに慣れていただく事は勿論大事だと思いますが、実際に災害が発生した時にはデジタル特有のインタフェースをできるだけ排除してはどうでしょうか。例えば避難所の出入り口をゲートの無い顔認証にするとか、スマホへの情報通知だけでなく壁新聞を廊下に張り出すとか、AIによる会話型の各種申請書作成とか、いろいろと手はあると思います。
防災だけでなく、病院の受付でもマイナンバーカードの顔認証も同様です。顔認証の際には情報を共有して良いかなど毎回同じで質問が繰り返されます。何とかならないでしょうかねぇ。大体あんな箱に顔を近づけて顔認証する意味が分かりません。顔認証は雑踏の中でも認識可能なくらい技術は進んでいますから、カメラ付きの小型のディスプレイで充分なはずなんですが。更に言えば、元々の保険証は顔写真の無いカードでした。それに対しマイナンバーカードは顔写真付きのカードなので格段にセキュリティーレベルは向上しています。そうであれば、デジタル的な認証が不得意であれば単なるフォトIDとして使う事も可能なはずです。情報共有するかどうかはどこかの時点で一度だけオプトインすれば良いだけです。例えば、マイナンバーカードの更新時とかですね。繰り返しますが、元々は顔写真もない低セキュリティーのカードだったのですから。利用者にデジタルなインタフェースを強要するのは余り賢いデジタル化とは言えないような気がします。今後は生成AIなどを活用した会話的なインタフェースが提供され、「今時スマホなんて古ーい」と言われる時代が来るような気がしています。
[付録] “デジタル”という言葉は理解可能なのか
「”デジタル”という言葉は理解可能なのか」という表題でコラムを書き始めましたが、筆者の結論としては「できない」か「かなり困難」だと考えています。
生成系AIが隆盛を誇っていますが、果たしてAIは本当に物事を理解できるのでしょうか。この問いは生成系AIが生まれる前の1990年頃から議論されていて、未だに結論は得られていません。この問いを「記号接地問題」と言います。記号とは、コンピューターに読み込ませた大量の言葉の事です。つまり、言葉だけを大量に覚えても本当に物事を理解したことになるのだろうかという問いです。そして、接地とは人間の実体験の事です。例えばリンゴは赤いと言えば、リンゴを見たことがある人間は「ああ、あの色の事だな」と理解出ます。一方、コンピューターは言葉として知っているだけで「ああ、あれね」とはなりません。AIは記号を大量に覚えて記号を出力する訳ですから、結局メリーゴーランドの様にぐるぐる回っているだけで地面にはたどり着けない。本当には理解できないのではないかという問いです。
翻って人間について考えてみます。人間が「おぎゃー」と生まれると、記号(言葉)を覚える前に接地(実体験)から経験し始めます。例えばミルクを飲んだり誰かに抱かれたりして、色々な経験を始めます。その内、色々な接地(経験)に対して記号を割り当てていきます。何かを食べたてる状況に「マンマ」という音が関係する様だという感じです。この状態では食べるものがマンマなのか、食べる行為がマンマなのか、その場所がマンマなのかは分かりませんが、経験を繰り替えていくうちに記号が何に対応するのかを段々明確にしていきます。その様な経験を色々と重ねていくうちに人間は成長し、多くの記号を確固たる接地の上に組み立てることが出来るようになります。
ところがある日、自分が接地している記号群には無い記号が目の前に現れる事になります。小学生でしたら「足し算」、中学生でしたら「方程式」で躓いた方も多いと思います。そこで学校の先生は、足し算の前に「ミカンがひとつとミカンが二つで合わせて幾つ?」と問いかけたり、方程式の前に「鶴亀算」を実際に指を追って数えてみたりして先に接地点を作る様に指導を試みます。大事なのは「前に」という部分です。これが逆転すると理解を難しくします。さて、”デジタル”という記号が示す概念の理解はどうでしょうか。デジタルは直接接地していない抽象的な概念(ひょっとすると概念ですらないバズワード)なので、デジタルをそのまま理解する事は出来ません。デジタルと言われるものに含まれるより抽象性の低く(つまり接地性が高い)経験ができる幾つかの概念を先に理解してそこから類推するしか手が無いのです。ここで例をひとつあげましょう。「動物」について個々の種を持ちいることなしに説明できるでしょうか。不可能とは言いませんが、筆者にはとても説明できそうにありません。説明するとしたら、「猫とか犬の類だよ」と説明する方がよほど早いです。なぜなら猫や犬は実際に見たことがあり、接地しているからです。次に動物園に連れて行って「もっと沢山の種類の動物がいるんだよ」と説明し、動く生き物を「動物」という記号であらわすという事をその後で説明します。
さて、”デジタル”-はどうでしょう。デジタルという言葉は既に世の中に出回っていますから、今更デジタルを知る”前に”経験をさせる事は出来ません。そこで一旦「デジタルという言葉自体には意味が無く理解する必要が無い」と引き戻す事が必要です。そしてその上で、”動物”と同様に例を挙げていくしかないですね。例えば以下の様なかんじです。
- 自動車: 今の自動車は人間はハンドルやペダルなどを操作するだけで、エンジンとモーターの切り替えなどの面倒な操作は自動車が勝手にやってくれるんだよ
- エアコン: 人間は目標の温度を設定するだけで、強弱の調整などはエアコンが勝手にやってくれるんだよ
- 人感センサ付き照明: 人が居るかどうかを証明が勝手に判断して点灯してくれるんだよ
- 生成AI: 簡単な指示や質問をするだけで、答えてくれたり絵や音楽を作ってくれ便利な機能だよ
- 券売機: ボタンを押すだけで目的地までの切符を買う事が出来るんだよ
- レジ横のピッとするやつ: カードやスマホをかざすだけでお金を自動的に口座から引き落としてくれるんだよ
これくらい知っていればデジタルを理解している事になるのではないでしょうか。あ、もうひとつ大事なことを知っておく必要があります。
- 思ったように操作できないのはあなたが悪いのではなく、作ったエンジニアがアホなのか、或いは人間の技術力がまだまだ不十分だからだよ
- 人間にとって使いにくいことを「時が解決する問題」と呼び、本来、使う方の人間が自力で解決すべき問題ではないんだよ
ですね。